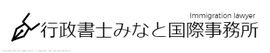監理団体の運営
1 報告・届出一覧
| 様式 | 届出先 | 期限 | |
| 1 | 技能実習実施困難時届出書 | 実習実施者の住所地を管轄する地方事務所・支所の認定課 | 届出事由発生後、遅滞なく |
| 2 | 監査報告書 | 監査対象実習実施者の住所地を管轄する地方事務所・支所の認定課 | 監査実施日から2か月以内 |
| 3 | 許可取消事由該当事案に係る報告書 | 監理団体の住所地を管轄する地方事務所・支所の指導課 | 報告事由発生後直ちに |
| 4 | 変更届出書 | 本部事務所の審査課 | 変更事由発生後1か月以内 |
| 5 | 変更届出書及び許可証書換申請書 | 本部事務所の審査課 | 変更事由発生後1か月以内 |
| 6 | 事業廃止届出書 | 本部事務所の審査課 | 廃止予定の1か月前 |
| 7 | 事業休止届出書 | 本部事務所の審査課 | 休止予定日の1か月前 |
| 8 | 事業再開届出書 | 本部事務所の審査課 | 再開予定日の1か月前 |
| 9 | 事業報告書 | 本部事務所の審査課 | 毎年4月から5月末日まで |
2 事業報告書
|
事業報告書は、監理事業を行う事業所ごとに作成します。
一般監理事業の場合は、優良要件適合申告書の添付が必要です。 |
|
【事業報告書記載事項】
【添付書類】
|
3 技能実習実施困難時届出
|
法第33条
監理団体は、第十九条第二項の規定による通知を受けた場合その他実習監理を行う団体監理型実習実施者が団体監理型技能実習を行わせることが困難となったと認めるときは、遅滞なく、当該通知に係る事項その他の主務省令で定める事項を主務大臣に届け出なければならない。 |
○ 監理団体は、実習実施者の事業上・経営上の都合、技能実習生の病気や怪我(労災を含む。)の事情等で技能実習を行わせることが困難となった旨の通知を受けた場合等には、実習実施者の住所地を管轄する機構の地方事務所・支所の認定課に遅滞なく技能実習実施困難時届出書(省令様式第18号)を提出しなければなりません。
○ 監理団体は、
・ 技能実習生が途中帰国することとなる場合:帰国日前まで
・ それ以外の理由で技能実習を行わせることが困難になった場合:困難になった 事由が発生してから2週間以内
に、技能実習実施困難時届出書を提出しなければなりません。提出を怠ったにもかかわらず機構の指導に従わなかった場合には、行政処分の対象となる可能性があるほか、罰則(30万円以下の罰金)の対象ともなります(法第112条第3号及び第8号)。
○ 技能実習生が技能実習計画の満了前に途中で帰国することとなる場合には、技能実習生に対し、意に反して技能実習を中止して帰国する必要がないことの説明や帰国の意思確認を書面(参考様式第1-43号)により十分に行った上、技能実習生の帰国が決定した時点で技能実習実施困難時届出書とともに帰国前に機構の地方事務所・支所の認定課へ届け出なければなりません。これは、旧制度において技能実習生の意に反して技能実習計画の満了前に帰国させるという事案が発生したことを受けたものです。 なお、技能実習生が途中帰国する方針が決まった時点で、当該書面を添付した上で必ず帰国する前に届け出て(郵送の場合は必着)ください。 ただし、帰国便の都合や帰国予定の技能実習生が期間満了日までに有給休暇をまとめて消化する等のやむを得ない事情がある場合など技能実習生の意に反するものでないことが確認できる場合には、参考様式(第1-40号)等により、帰国の意思確認を十分に行い、これらのやむを得ない事情があったことを記録しておく場合は、技能実習実施困難時届出書の提出は不要です。
○ 次段階の技能実習に移行予定の技能実習生が、現在の技能実習期間の満了前に次段階の技能実習に係る在留資格変更許可を受ける場合も、早期に移行した日数の分、全体の技能実習期間が短縮されることとなりますが、この場合も、参考様式(第141号)等により、技能実習生の同意が得られていれば、技能実習実施困難時届出書の提出は不要です。
○ 技能実習生が妊娠、出産等したことを理由とする解雇その他不利益な取扱いは、男女雇用機会均等法違反となります。妊娠・出産による中断等、技能実習を継続することができなくなった場合には、技能実習実施困難時届出書の提出が必要ですが、その際、監理団体・実習実施者は技能実習生向けリーフレット(https://www.otit.go.jp/info_kanri/)等を活用して、以下の事項について分かりやすく説明するなどし、技能実習生の希望も踏まえて必要な対応が求められます。
・ 母子健康手帳の交付、病院や市町村の窓口、技能実習生の定期的な病院受診の手続の説明や支援等
・ 技能実習を最後まで行えることの説明(地方出入国在留管理局で在留資格に係る相談ができることを含む。)、技能実習の継続の意思の確認、日本での出産希望の確認等
・ 技能実習生が帰国して母国で出産を希望する場合は、実習の再開の時期や手続の説明等
・ 出産育児一時金の支給、健康保険の出産手当金の支給の説明、産前産後休暇等の説明等
その上で、技能実習生が帰国することを希望した場合には、技能実習の継続や終了後の再開の意思を把握するための資料として、技能実習生本人が作成した 「妊娠等に関連した技能実習期間満了前の帰国についての申告書」(参考様式第1-42号)を、監理団体又は企業単独型実習実施者において保管するようにしてください。 また、一度技能実習を中断した後に、同じ実習実施者の下で技能実習を再開する場合には、新規の技能実習計画の認定は必要なく、変更認定 により行える こととしています。この場合は、技能実習を中断した理由及び再開するに至った経緯等を記載した理由書(様式自由) を提出することが必要となります(中断理由が自身の妊娠・出産等の場合にあっては、経緯等を記載した理由書に代えて、妊娠等に関連した技能実習期間満了前の帰国についての申告書(参考様式第1-42号) 写しを提出することも可能です。)。 なお、再開に際して人数枠の基準を満たしている必要があります(人数枠の特例は適用されません。)。 そのため、本人が出産等のため一度は帰国を希望する場合であっても、上記申告書を使用するなどして、 計画的に技能実習を再開することができるように実習再開の意思をあらかじめ確認し、再開する場合の時期、双方の連絡先などについて認識を共有しておくことが望まれます。
○ 病気・怪我による技能実習の中断については、入院を伴う治療等実習に全く従事することができず技能修得を行うことができなかったことが客観的に立証できる場合に限られるため、単に体調不良等を理由として数日間自宅で療養する場合など、技能実習を行わせることが困難となったものと認められないときは、再開は認められません。そのため、このような場合には、技能実習実施困難時届出書を提出することは不要となります。
○ 現在の実習実施者で技能実習を継続することができなくなった場合には、技能実習生が実習先を変更するなどして技能実習を継続したいとの希望を持っているかを確認することが必要となります。継続の希望を持っている場合には、他の実習実施者や監理団体等との連絡調整等の必要な措置を講じなければなりません(法第51条)。また、次の実習先が確保されるまでの間の技能実習生の待遇がどのようになっているのかなど、技能実習生の現状(入国状況、住宅の確保、休業手当や雇用保険の受給状況を含む生活費等の確保)や技能実習の継続のための措置(転籍等の連絡調整等の状況、帰国する場合は帰国理由や予定時期等)を含めて届け出る必要があります。
○ 「実習先の変更」については、実習実施者の経営上・事業上の都合、実習認定の取消し、実習実施者における労使間の諸問題、実習実施者における暴行等の人権侵害行為や対人関係の諸問題等、現在の実習実施者の下で技能実習を続けさせることが、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護という趣旨に沿わないと認められる事情による場合に認められます。なお、専ら技能実習生の都合によるものは認められません。
○ 「必要な措置」とは個々の技能実習生の置かれた状況に応じて必要な支援を行うものであり、様々な支援を行うことが想定されますが、例えば技能実習生が新たな実習先が決定するまでの間に宿泊する場所がない場合については、当面の間、宿泊することができる施設を確保することや日常生活に関する支援を行うなどが想定されます。 なお、当該措置に要する費用については、監理に要する費用であるため、技能実習生本人に直接又は間接に負担させることは認められませんが、技能実習生に代わって監理団体等が自ら賃借人となって賃貸借契約を締結した上で、当該技能実習生合意の下、当該技能実習生に対して住居として提供する場合などについては、当該費用を実費に相当する適正な額に限って、技能実習生から当該費用を徴収することは差し支えありません。
○ なお、実習実施者や監理団体が責任を持って次の実習先を確保することが必要ですが、機構が行う実習先変更支援のサービスを利用することも可能です。 ○ 省令様式第18号に記載する内容が、同様式の記の「3の① 認定番号」欄、「3の② 認定年月日」欄及び「4 技能実習生」欄以外の記載が全て同一のときは、それら3つの欄の記載について、別紙を用いて表形式で記載すれば、同様式の提出は1通にまとめて届け出をすることも可能です。
○ 技能実習生の妊娠・出産等を理由に、技能実習生の意に反して一方的に技能実習を打ち切った場合であって、監理団体がそれを知りながら、何ら措置を講じていなかった場合は、認定計画に従って実習監理を行っていないものとして、監理団体の許可の取消しの対象となります。
○ 技能実習生が失踪した場合について 技能実習生の行方が分からなくなるなど失踪の疑いが生じたことを把握した場合については、送出機関等と連携しながら、本国の緊急連絡先(技能実習生の家族等)に対して確認するなどにより所在把握に努めてください。 その上で、技能実習を行わせることが困難となった場合には、該当することから、機構の地方事務所・支所の認定課への技能実習実施困難時届出が必要となります。いったん失踪した技能実習生が失踪前の実習実施者に復帰し、技能実習の再開を希望する場合の取扱いについては、別途機構地方事務所に御相談ください。なお、失踪した技能実習生については、入管法上の在留資格の取消手続の対象となります。
4 監査について
|
【確認対象の書類】 ・ 監理団体許可申請書(省令様式第11号) ・ 監理事業計画書(省令様式第12号) ・ 申請者の誓約書(参考様式第2-2号) |
|
○ 監査を実施するにあたり、監理団体は、技能実習生が認定計画と異なる作業に従事していないか、実習実施者が出入国又は労働に関する法令に違反していないかなどの事項について、監理責任者の指揮の下で、3か月に1回以上の頻度で、実習実施者に対して適切に行うことが必要です。 ※ 監理責任者は監理団体が行う監理事業の統括責任者です。そのため、監査に当たっては、監理責任者が自らの指揮の下、監査の実務を担当する監理団体の役職員とともに適切に行う必要があります(当然のことながら、監査は監理団体が行う監理事業の根幹業務ですので、外部に委託することができないことは言うまでもありません。)。 ※ なお、監理責任者は、実習実施者の役職員若しくは過去5年以内に役職員であった場合や、これらの者の配偶者若しくは二親等以内の親族である場合は、当該実習実施者の実習監理を行うことはできず、他の監理責任者を新たに選任し、実習監理を行わせる必要があります(規則第53条)。 ※ 「3月に1回以上の頻度」とは、入国後講習開始日の属する月を起算月とする3月(四半期)ごとに少なくとも1回監査を実施するということです。 例えば、入国後講習開始日が4月16日である場合は、6月30日までに監査を実施する必要があり、次回は、7月1日から9月30日までの期間に、監査を実施することになります。 なお、適正な実習監理の観点からは、定期的に技能実習の実施状況を確認することが妥当であることから、前回監査実施日を起算日として3か月以内ごとに監査を実施することが望ましいと考えられます。
○ 監査を行った場合には、監査を行った日から2か月以内に、監査報告書(省令様式第22号)により、その結果を対象の実習実施者の住所地を管轄する機構の地方事務所・支所の指導課に報告することとなります。
○ 監査の際には、原則として、 ①技能実習の実施状況を実地に確認すること、 ②技能実習責任者及び技能実習指導員から報告を受けること、 ③技能実習生の4分の1以上と面談すること、 ④実習実施者の事業所の設備、帳簿書類等を閲覧すること、 ⑤技能実習生の宿泊施設等の生活環境を確認すること、が必要です。
○ 一方で、例えば部外者の立入りが極めて困難な場所で実習が行われているため①の方法によることができない場合など技能実習生が従事する業務の性質上①~⑤のうちの一つ又は複数の方法について著しく困難な事情がある場合には、当該方法に代えて他の適切な方法をとることが可能です。この場合は、その理由と他の適切な監査方法を監査報告書(省令様式第22号)の特記事項欄に記載することになります。
【留意事項】
○ 監理団体が監査において確認する内容について
・ 実習実施者に対する定期監査においては、技能実習の運用上問題が生じやすい部分を重点的に確認することが必要です。 運用上問題が生じやすい部分として、例えば、割増賃金の不払、労働時間の偽装、技能実習計画とは異なる作業への従事、実習実施者以外の事業者での作業従事、不法就労者の雇用、入国後講習期間中の業務への従事、暴力、脅迫やハラスメント等の人権侵害行為などが、過去の不正行為事例として多く認められています。
・ 「認定計画と異なる作業に従事していないか」「雇用契約に基づき適切に報酬が支払われているか」「旅券・在留カードの保管を行っていないか」など事実関係について確認し、技能実習計画に従って技能実習を行わせていない事実、出入国・労働関係法令に違反する事実があれば、適切に指導を行わなければなりません。
・ 「認定計画と異なる作業に従事していないか」については、実習実施予定表と照合して確認するだけでなく、技能実習生が移行対象職種・作業に従事している場合には、作業内容が審査基準に定める必須業務等に合致しているかを必ず確認しなければなりません。 監査は上記のとおり確認の上、必要な指導を行うものであり、このような確認や指導が適切に行われていない場合、十分な監査が行われているとは言えません。
○ 技能実習生が従事する業務の性質上①~⑤の方法によることが著しく困難な場合について
・ ①~⑤の方法によることが著しく困難な場合とは、例えば、次に記載するような場合などを想定しており、やむを得ない場合に限られます。それぞれの場合の他の適切な監査方法については、例えば、次に記載するような監査方法が想定されます。 - 安全上の観点から立入りができず、技能実習生の稼働状況を遠目に見ることも困難な建設現場での実習の場合 - 衛生上の観点から従業員以外の立入りが禁止されている食品工場での実習の場合 (他の適切な監査方法) ・実地での確認を省略する代わりに、技能実習生に対し実習現場近くで面談して話を聴く等 ・建設現場の場合は、元請事業者の現場代理人等から作業状況等を聴取する等 ・WEBカメラ等を利用して、実際に作業を行っているところを確認する等
○ 技能実習生との面談について
・ 技能実習生との面談については、技能実習生ごとに個別に面談する方法のみならず、複数の技能実習生に対して集団で面談する方法なども考えられます。また、面談の全ての過程を必ず口頭で行わなければならないわけではなく、例えば、その場で簡単な質問票を配付して回答を得た上で、回答を踏まえ項目を絞って面談を行うような方法も考えられます。
・ 1回の監査につき技能実習生の4分の1以上と面談しなければならないこととされており、3月に1回以上の監査によって全ての技能実習生と面談することが望まれます。
・ 受け入れている技能実習生が1人など少数の場合には、技能実習生が監査当日病気等の事情で欠勤したことにより、監査の訪問時に所定の数の技能実習生との面談が難しい場合がありますが、そのような場合に、必ず欠勤した技能実習生と面談することを求める訳ではありません。このような場合には、次回の監査などの際に当該技能実習生と必ず面談できるよう調整するといった対応をすることも可能です。
・ 技能実習生との面談においては、技能実習生の日本語の理解能力に応じて、通訳人を使用したり、「最近どこでどんな仕事をしていますか」「先月の給料はいくら受け取りましたか」といった平易な日本語を用いて質問をしたりすることや、技能実習生手帳を用いて重要な部分を参照しながら説明を行うことなどが効果的と考えられます。
・ 面談において、技能実習生から実習内容や雇用契約の内容について要望や相談があり、その内容が技能実習法違反等の疑いがある場合には速やかに実習実施者に確認し、改善させるとともに、機構や関係行政機関に報告・通報する必要があります。
・ また、技能実習を継続していく上で支障が生じるおそれがあるような内容や状況を把握した場合(例えば、仕事がきつい、指示がわからない、もっと休みが欲しい、いつもつらそうにしている、仕事のことを考えると眠れなくなるなど)があった場合は、実習実施者と相談の上、技能実習生の負担軽減のための業務上の配慮をしたり、技能実習生とのコミュニケーションを図る方法を見直す等の対応を行うことが求められます(技能実習計画の変更が生じる場合には、機構への届出等が必要になる場合があります。)。
・ 技能実習生は、母国とは大きく異なる生活環境や人間関係等の中で技能実習を行っており、ストレスを受けやすい環境に置かれていると考えられます。このため、面談においては、メンタルヘルス面での問題がないかも技能実習生に確認し、問題や相談があれば適切に対応するなど、メンタルヘルス確保の観点にも留意して行うことが求められます。
・ 技能実習生から要望や相談が寄せられない場合であっても、面談や監査を通じて、現在の実習の環境が技能実習生にとって大きな負担となっていないかを十分に確認し、負担となっていると判断される場合は、上記と同様の対応を取ることが望まれます。
※ 監理団体は、技能実習生と雇用関係にはないため、技能実習生に対して、パワーハラスメント等の防止について労働施策総合推進法における雇用管理上の措置義務を負うものではありません。しかし、監理団体は、技能実習法令上、技能実習生の保護に関する役割のみならず、実習実施者が技能実習に関し労働関係法令に違反しないよう、必要な指導を行う役割があることを認識の上、監理責任者自ら又は監理団体の役職員が技能実習生に対してパワーハラスメント等に類する言動等を行わないよう、雇用管理上の措置の内容を参考にしつつ、適切な対応に努めてください。
○ 事業所の設備・帳簿書類の確認について
・ 事業所の設備・帳簿書類の確認に当たっては、例えば以下のような点に留意することが必要です。
- 技能実習計画に記載された機械、器具等の設備を用いて、安全衛生面に配慮して、技能実習計画に記載されたとおりに技能実習が行われていること - 賃金台帳、タイムカードなどから確認できる技能実習生に対して支払われた報酬や労働時間が技能実習計画に記載された内容と合致していること - 技能実習生に対する業務内容・指導内容を記録した日誌から、技能実習生が技能実習計画に記載された業務を行っていること
○ 宿泊施設等の生活環境の確認について
・ 宿泊施設等の生活環境の確認に当たっては、例えば以下のような点に留意することが必要です。
- 宿泊施設の衛生状況が良好であるか - 宿泊施設の1部屋当たりの実習生数が何名となっているか - 不当に私生活の自由が制限されていないか - 鍵の付いた私物保管設備はあるか
・ 宿泊施設が離れた場所で複数に分かれており、毎回全てを確認することが困難な場合には、複数回の定期監査に分けて各宿泊施設を訪れるということでも構いません。その場合においても、複数回の定期監査により全ての宿泊施設を訪れることが望まれます。
臨時監査に関するもの
○ 3か月に1回以上の頻度で行う監査のほか、実習実施者からの報告や技能実習生からの相談等により、法第16条第1項各号(実習認定の取消し事由)のいずれかに該当する可能性がある場合には、監理団体は直ちに臨時の監査を行うことが必要となります。
○ この臨時の監査については、実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないなどの情報を得たときはもとより、実習実施者が不法就労者を雇用しているなど出入国関係法令に違反している疑いがあるとの情報を得たとき、実習実施者が技能実習生の労働災害を発生させたなど労働関係法令に違反している疑いがあるとの情報を得たときなどにも行うことが求められます。
○ 特に、技能実習生に対する暴行、脅迫その他人権を侵害する行為が疑われる情報を得た場合については、迅速かつ確実に臨時監査を実施する必要があります。 また、臨時監査後、電話等により、その概要を直ちに実習実施者の住所地を管轄する機構の地方事務所・支所の指導課に連絡するとともに、当該監査の実施結果については、監査報告書によりとりまとめの上、速やかに同課に報告する必要があります。 具体的には、監査報告書について、技能実習生の保護や早期の事案の解明が求められることから、臨時監査実施後、遅くとも2週間以内に報告することが求められます。
【留意事項】
○ 臨時監査の位置付けについて
・ 実習実施者が法第16条第1項各号(実習認定の取消し事由)のいずれかに該当する疑いがあると監理団体が認めた場合に直ちに行う監査を、便宜上臨時監査と呼んでいます。この臨時に行う監査についても、上記の疑いがある事項を確認するほか、定期監査と同じ項目においても確認することにより、規則第52条第1号に規定する監査の一つとすることができます。したがって、定期監査又は上記臨時監査が3か月以内に行われていればよく、必ずしも定期監査を3か月に1回以上の頻度で臨時監査とは別に実施しなければいけないわけではありません。 |
5 訪問指導について
○ 訪問指導とは、第1号技能実習の場合に、監査とは別途、技能実習生が実習実施者における技能実習を開始したときから、監理責任者の指揮の下に、1か月につき少なくとも1回以上(※)、監理団体の役職員が実習実施者に赴いて技能実習の実施状況を実地に確認するとともに、認定された技能実習計画に基づいて技能実習を適正に行わせるよう必要な指導を行うことです。
※ 「1月に1回以上の頻度」とは、入国後講習修了後に、実習実施者における技能実習を開始した日が属する月を起算月として、各月のいずれかの日に少なくとも1回の訪問指導を実施するということです。 例えば、実習実施者における技能実習開始日が4月16日である場合は、4月30日までに訪問指導を実施する必要があり、次回は、5月1日から5月30日までの期間に、訪問指導を実施することになります。
○ 訪問指導を行った場合は、指導の内容を記録した訪問指導記録書(参考様式第410号)を作成し、事業所に備え付けなければなりません。また、この訪問指導の書類の写しは、事業報告書に添付し、年に1度機構の本部事務所の審査課に提出しなければなりません。
○ 第1号技能実習については、技能実習生を取り巻く環境に大きな変化がある中で行われていることから、訪問指導の際は、実習実施者に対して、技能実習生のメンタルヘルスの配慮に努めているか確認及び指導を行うなど、メンタルヘルスの確保が図られるよう特に留意する必要があります。
【留意事項】
○ 訪問指導を担当する者について
・ 訪問指導は、技能実習の初期段階である第1号技能実習を行わせるに当たって、監理団体が作成の指導を行った技能実習計画に基づいて技能実習を適正に行わせているかを確認するものであるため、実習実施者に対して適切な指導を行うことができるように技能実習計画の作成の指導を担当した者が実施するのが望ましいと考えられます。
・ また、実習監理を行う実習実施者の数や所在地などの関係から、技能実習計画の作成指導者のみで全ての訪問指導に対応することが困難な場合には、他の役職員がその技能実習計画作成指導者から事前に必要な説明を受けるなどした上で、訪問指導を実施することが望ましいと考えられます。
○ 技能実習生が従事する業務の性質上実地確認によることが著しく困難な場合について
・ 前述「(1)監査に関するもの」に記載の考え方と同様の考え方に基づき、「実地確認によることが著しく困難な場合」であるか否かを判断することになります。
6 制度趣旨に反した方法での勧誘等
|
○ 法第3条第2項の基本理念でも明示されているとおり、技能実習が、労働力の需給の調整の手段として行われることはあってはなりません。
○ この制度趣旨を正しく理解せず、労働力の需給の調整の手段として技能実習を行わせようとする実習実施者や監理団体は、受入れ機関としてふさわしくありません。
○ 監理団体の業務実施基準(規則第52条第4号)においても、制度の趣旨に反して技能実習を労働力の需給の調整の手段であると誤認させるような方法で、実習実施者の勧誘又は監理事業の紹介をすることを禁止しています。具体的には、例えば、監理団体が、そのホームページやパンフレットなどで、技能実習生の受入れが人手不足対策になるといったような宣伝や広告を出すことは不適切な勧誘や紹介となります。 |
7 外国の送出機関との契約内容
|
○ 外国の送出機関については、法第23条第2項第6号に基づき、その要件が規則第25条に定められているところであり、監理団体は、外国の送出機関から求職の申込みの取次ぎを受けようとする場合にあっては、外国の送出機関との間で当該取次ぎに係る契約を締結することが求められています(後述P218参照)。
○ これに加え、監理団体は、外国の送出機関が保証金、違約金の徴収を行うような契約を結んでいないことについて確認し、その旨を外国の送出機関との取次ぎに係る契約書に記載しなければなりません(規則第52条第5号)。
○ 監理団体と取次送出機関との間で、技能実習生が失踪した場合等技能実習に係る契約の不履行について、違約金(名称はこれに限定されません。)を定める契約を結ぶことも認められません。
○ これは、技能実習生等から保証金、違約金の徴収を行うような外国の送出機関はふさわしくないため、そのことを監理団体においても確認し、外国の送出機関との契約書において明記することを求めるものです。
○ 監理団体自らが外国の送出機関と、技能実習に係る契約の不履行についての違約金契約やキックバックなどの不当な利益を得る契約を締結している場合には、監理許可が取り消されることがありますので、外国の送出機関と契約を締結する際には、相手任せにせず、確実に契約内容を確認してください。 |
8 技能実習生の帰国旅費の負担について
|
○ 監理団体は、技能実習生の帰国旅費を負担するとともに、技能実習の終了後の帰国が円滑にされるよう必要な措置を講じなければなりません。
○ 技能等を移転するという技能実習制度の趣旨に鑑みて、技能実習生の帰国に支障を来さないようにするために、監理団体が帰国旅費の全額を負担することとしているものです。
○ また、第3号技能実習開始時の渡航旅費については、第2号技能実習を行っている間に第3号技能実習に係る技能実習計画の認定申請を行った場合には、第3号技能実習を行わせる監理団体が負担することとなります。これは、第3号技能実習開始前の一旦帰国を確実なものとするため、一旦帰国する際の旅費の負担を監理団体に求めているものです。
※ 第2号技能実習と第3号技能実習の実習実施者が異なる場合、第2号技能実習終了後の一旦帰国時の帰国旅費については第2号技能実習を行わせた監理団体が、第3号技能実習開始前の日本への渡航旅費については第3号技能実習を行わせる監理団体が、それぞれ負担することとなります。
※ ただし、例えば5年前に第2号技能実習を終えて帰国した者が、改めて第3号技能実習を行いたいとする場合にまで、その渡航旅費の負担を監理団体に求めるとした場合、日本への渡航旅費の負担を特段規定していない第1号技能実習の場合と比較しても合理的とはいえないため、第2号技能実習を行っている間に第3号技能実習に係る技能実習計画の認定申請を行った場合にのみ、一旦帰国後の日本への渡航旅費について、監理団体の負担としています。
○ 帰国事由が技能実習生の自己都合による場合について 監理団体が負担すべき帰国旅費については、帰国事由を限定していません。帰国事由が技能実習生の自己都合による場合であっても、帰国旅費の負担が監理団体が負います。 これは、技能実習生と監理団体との間で「自己都合」に関して解釈に争いが生じ、結果として、技能実習生の帰国に支障を来すことを防ぐためです。 |
9 技能実習計画の作成指導
|
○ 監理団体が実習実施者の作成する技能実習計画について指導するに当たっては、技能実習を行わせる事業所と技能実習生の宿泊施設を実地に確認するほか、認定基準及び出入国又は労働に関する法令への適合性の観点、適切かつ効果的に技能等の修得等をさせる観点、技能実習を行わせる環境を適切に整備する観点から指導を行わなければなりません。
○ 特に、適切かつ効果的に技能等の修得等をさせる観点からの指導については、監理団体の役職員のうち、技能実習生に修得等をさせようとする技能等について一定の経験や知識がある者が行わなければなりません。 なお 、この作成指導は、監理団体が自ら行わなくてはならないため、監理団体と雇用契約がない者を技能実習計画作成指導者とした上で、実習実施者に技能実習計画の作成指導を行わせた場合は、名義貸し(法38条)に該当するおそれがあります。
○ また、技能実習計画作成指導者は、実習実施者が技能実習生に従事させようとする作業が、技能実習を行わせる事業所において通常行われている内容であることを確認するとともに、当該作業が移行対象職種・作業に係るものである場合には、実習実施者に審査基準を丁寧に説明するなどして、定められている業務の内容が必須業務等として実施可能であるかを、必ず確認しなければなりません。
【留意事項】
○ 修得等をさせようとする技能等について一定の経験又は知識を有する役職員について
・ 修得等をさせようとする技能等について一定の経験又は知識を有すると認められる技能実習計画作成指導者は、監理団体の役職員(常勤・非常勤は問わない。)であって、「取扱職種について5年以上の実務経験を有する者」か「旧制度において取扱職種に係る技能実習計画の作成経験を有する者」である必要があります。 ・ 5年以上の実務経験として求められるレベルとしては、厳密な作業レベルまで一致する経験を求められるわけではなく、例えば、移行対象職種・作業の単位で一致する経験を有していることまでではなく、職種単位で一致する経験であれば作業の単位で異なる経験であったとしても認められることとなります。 ・ 旧制度において取扱職種に係る技能実習計画の作成経験を有する者には、単に補助者として技能実習計画の作成を手伝ったり、助言にとどまる場合は含まれません。 ・ 技能実習計画作成指導員は、上記条件以外に特段の資格等の取得が求められるものではありません。 ・ 監理団体許可申請書(省令様式第11号)の「1申請者⑨団体監理型技能実習の取扱職種の範囲等」や監理事業計画書(省令様式第12号)の「6団体監理型技能実習の取扱職種の範囲等」に記載された全ての取扱職種について、技能実習計画作成指導者が確保されている必要がありますが、全ての取扱職種を1人が担当しなければならない訳ではなく、2人以上で取扱職種ごとに分担して担当することも認められます。
○ 技能実習計画作成指導者の人数等について
・ 取扱職種ごとに、要件を満たす技能実習計画作成指導者が常勤・非常勤であるかを問わず、監理団体の役職員の中から確保されていることを要しますが、監理団体の事業所ごとに専属の技能実習計画作成指導者が確保されていなければならないわけではありません。 |
10 相談体制の整備
|
○ 監理団体に相談体制の構築を求める趣旨は、実習実施者において技能実習生が人権侵害行為を受けている事案など実習実施者の技能実習指導員や生活指導員などの役職員に相談できない場合において、監理団体が技能実習生を保護・支援できるようにするためです。また、監理団体に、受け入れている技能実習生の国籍(国又は地域)に応じた相談応需体制を整備させることにより、実習実施者のみでは体制整備が困難な母国語での相談を可能とするものです。
○ 技能実習生からの相談内容に係る対応については、監理事業に従事する役職員が行わなければならず、その内容に応じて、公的機関や実習実施者の生活指導員等と連携して適切に対応する必要があります。技能実習生からの相談に対応した場合は、団体監理型技能実習生からの相談対応記録書(参考様式第4-11号)を作成し、事業所に備え付けなければなりません。相談対応記録書の作成に当たっては、相談内容や対応内容が明らかになるよう具体的に記載することが望まれます。
○ 技能実習生からの相談は、技能実習を行っている時間帯のみならず、夜間、休日にも想定されることを踏まえ、それらの時間帯にも適切に相談応需体制を整備する必要があります。
【留意事項】
○ 通訳人について ・ 通訳人は、技能実習生からの相談を母国語で受け付ける役割を担う者ですが、必ずしも監理団体の常勤職員であることまでは求められていません。非常勤の職員が従事することや、通訳業務自体を外部委託することも可能です。ただし、通訳業務を外部に委託したとしても、監理団体の役職員が責任を持って相談に応じなければならないことに変わりはありません。特に監査における技能実習生のヒアリングに際しては、積極的に通訳人の活用を図ることが望ましいといえます。また、中立的な相談応需体制の整備の観点から、実習実施者や送出機関の職員及びその関係者を通訳人とするのは望ましくありません。
○ 技能実習生への相談方法等の周知について ・ 監理団体は、技能実習生が相談したい場合に、いつ誰に連絡したら相談を受けられるのかが分かるよう、監理団体の連絡先等を示すとともに、相談方法等について、入国後講習の法的保護情報の科目の講義の際に必須教材とされている技能実習生手帳の該当箇所を示すなどにより、機構をはじめ、利用できる機関について技能実習生に対して詳しく周知する必要があります。 ・ 監理団体は、実習実施者と連携して、技能実習生が健康で快適な実習生活を送れるようにするため、食生活・医療等についての適切な助言及び援助を行うことができる体制を整備する必要があります。相談対応に当たっては、実習に関すること以外にも相談に応じる必要があり、相談内容によっては、国や自治体等が行っている各種行政サービスや医療機関の窓口への付き添い等のサポートを行いながら利用を促すことが求められます。 ・ 技能実習生からの相談には、相談しやすい環境をつくるとともに、相談に速やかに対応することが重要です。また、監査における面談等を通じて日頃から良好な関係性を築いておくことにより、技能実習生の悩みや体調の変化を把握することが重要です。 ※ 監理団体は、技能実習生と雇用関係にはないため、技能実習生に対して、パワーハラスメント等の防止について労働施策総合推進法における雇用管理上の措置義務を負うものではありませんが、同法の趣旨を踏まえるとともに、監理団体には技能実習生の保護に関する役割があることを認識の上、監理団体の役職員が技能実習生に対してパワーハラスメント等に類する言動等を行わないよう、雇用管理上の措置の内容を参考にしつつ、適切な対応に努めてください。 |
11 外部役員及び外部監査
|
○ 技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を実現するためには、監理団体が実習実施者に対して指導・監督を適切に行うことを担保し、監理団体が中立的な業務の運営を行うことが不可欠です。
○ 一方で、監理団体が、その組合員たる実習実施者を実習監理するに際し、中立的な業務の運営を行うことが難しい側面も存在することも事実です。このため、外部役員を置くこと又は外部監査の措置を講じることのいずれかの措置を監理団体が講じていることを法律上義務付け、外部の視点を加えることにより、監理団体の業務の中立的な運営を担保しようとするものです。
<外部役員を置く方法>
○ 指定外部役員は、実習実施者に対する監査等の業務が適正に実施されているかの確認を、法人内部から担当する役員であり、監理団体の外部役員の中から指定を受けた者です。過去3年以内に外部役員に対する講習(第8章の主務大臣が告示した養成講習機関が実施する講習)を修了した者でなくてはなりません。
○ また、外部役員は、その「外部」性を担保する観点から、以下のような者であってはならないこととされています。 ① 実習監理を行う対象の実習実施者又はその現役若しくは過去5年以内の役職員 ② 過去5年以内に実習監理を行った実習実施者の現役又は過去5年以内の役職員 ③ ①②の者の配偶者又は二親等以内の親族 ④ 申請者(監理団体)の現役又は過去5年以内の役職員(監理事業に係る業務の適正な執行の指導監督に関する専門的な知識と経験を有する役員及び指定外部役員に指定されている役員を除く。) ⑤ 申請者(監理団体)の構成員(申請者が実習監理する団体監理型技能実習の職種に係る事業を営む構成員に限る。)又はその現役又は過去5年以内の役職員 ⑥ 傘下以外の実習実施者又はその役職員 ⑦ 他の監理団体の役職員(監理事業に係る業務の適正な執行の指導監督に関する専門的な知識と経験を有する役員及び指定外部役員に指定されている役員を除く。) ⑧ 申請者(監理団体)に取次ぎを行う外国の送出機関の現役又は過去5年以内の役職員 ⑨ 過去に技能実習に関して不正等を行った者など、外部役員による確認の公正が害されるおそれがあると認められる者
○ 指定外部役員には、監理団体の各事業所について監査等の業務の遂行状況を3か月に1回以上確認し、その結果を記載した書類を作成することが求められます。
<外部監査の措置を講じる方法>
○ 外部監査人は、実習実施者に対する監査等の業務が適正に実施されているかの監査を、法人外部から実施する者として、監理団体から選任を受けた者であり、法人・個人のいずれでも外部監査人になることが可能です。過去3年以内に外部監査人に対する講習(第8章の主務大臣が告示した養成講習機関が実施する講習)を修了した者でなくてはなりません。
○ また、外部監査人は、その「外部」性を担保する観点から、以下のような者であってはならないこととされています。 ① 実習監理を行う対象の実習実施者又はその現役若しくは過去5年以内の役職員 ② 過去5年以内に実習監理を行った実習実施者の現役又は過去5年以内の役職員 ③ ①②の者の配偶者又は二親等以内の親族 ④ 申請者(監理団体)の現役又は過去5年以内の役職員 ⑤ 申請者(監理団体)の構成員(申請者が実習監理する団体監理型技能実習の職種に係る事業を営む構成員に限る。)又はその現役又は過去5年以内の役職員 ⑥ 傘下以外の実習実施者又はその役職員 ⑦ 他の監理団体の役職員 ⑧ 申請者(監理団体)に取次ぎを行う外国の送出機関の現役又は過去5年以内の役職員 ⑨ 法人であって監理団体の許可の欠格事由(法第26条)に該当する者、個人であって監理団体の許可に係る役員関係の欠格事由(法第26条第5号)に該当する者 ⑩ 過去に技能実習に関して不正等を行った者など、外部監査の公正が害されるおそれがあると認められる者
○ 外部監査人には、監理団体の各事業所について監査等の業務の遂行状況を3か月に1回以上確認し、その結果を記載した書類を作成・監理団体へ提出することが求められます。
○ また、外部監査人は監理団体の役職員ではなく、監理団体が行う監査等の業務に従事することがないことから、監理団体が行う実習実施者への監査に、監理団体の各事業所につき1年に1回以上同行して確認し、その結果を記載した書類を作成・監理団体へ提出することが求められます。
【留意事項】
○ 申請者(監理団体)の現役又は過去5年以内の役員であっても指定外部役員に指定できる場合 ・ 申請者(監理団体)の現役又は過去5年以内の役員であっても、「監理事業に係る業務の適正な執行の指導監督に関する専門的な知識と経験を有する役員」であれば、外部役員に指名することは可能です。具体的には申請者(構成員を含む。)以外での人事労務管理・監査等の業務経験を有しており、出入国又は労働関係法令や監査についての専門的な知識と経験を活かして、他の役員及び職員を指導できる者であることが必要となります。 ・ 例えば、既に申請者(監理団体)の役員になっている方であっても、事業協同組合のいわゆる員外理事であって、企業において人事労務管理に携わっていた経験等を活かして監理事業に従事する方のような場合には、他の要件を満たせば、指定外部役員として指名することは認められます。 ・ また、例えば、監理団体の許可の有効期間の更新等の申請を行う際に、申請者(監理団体)の中で当該申請時に既に「指定外部役員に指定されている役員」についても、引き続き外部役員に指名することは認められます。
○ 申請者(監理団体)の構成員であっても指定外部役員に指定することや外部監査人に選任することができる場合 ・ 申請者(監理団体)の構成員であっても、「申請者が実習監理する団体監理型技能実習の職種に係る事業を営む構成員でない場合」であれば、指定外部役員に指名することや外部監査人に選任することが可能です。これは、申請者が実習監理する技能実習の職種に係る事業を営む構成員でない構成員は、通常技能実習に関与していないと考えられることから、「外部」と判断することを可能とするものです。 ・ 例えば、申請者(監理団体)の構成員であっても、会計事務所など、申請者が実習監理する予定の職種と関係のない会社の役職員であれば、他の要件を満たせば、外部役員として認められます。
○ 外部役員が担う業務範囲について ・ 外部役員に就任した者が、自ら監査業務等の監理団体の中核業務を担当することは、特段禁止されていません。外部の視点を活かして、自ら業務に当たることも可能です。 ・ 外部役員は、常勤・非常勤を問いません。
○ 外部役員・外部監査人の兼務について ・ 外部役員・外部監査人については、要件を満たす者であれば、複数の監理団体の外部役員・外部監査人を兼務することも可能です。 ・ 外部役員については、例えば、事業協同組合のいわゆる員外理事であって、企業において人事労務管理に携わっていた経験等を活かして監理事業に従事する方は、他の要件を満たせば、既に他の監理団体の役職員となっている場合であっても外部役員として認められることとなります。 ・ ただし、既に特定の監理団体の外部役員になっている者が、他の監理団体の外部監査人を兼務することはできません。 |
|
ご相談・ご依頼は
就労ビザについてのご相談・ご依頼は
面談相談 平日は20時まで、土曜日も対応できます。
私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。
ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。
相談料は、1時間5,500円です(消費税込み)
行政書士みなと国際事務所
- 名 称 行政書士みなと国際事務所
- 代表者 行政書士 宮本哲也
- 所在地 〒231-0004 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F
- GoogleMapはこちら
- 電 話 045-222-8533 (月-金10:00~18:00)
- FAX 045-222-8547 (24時間受付)
- 営業時間 月~金 10:00~18:00